ラーメン屋の接客に学ぶ触診の極意
去る10月5日、6日は整動協会会員限定の合宿に参加してきました。年間約30回組まれているセミナーの中で泊まり込みになるのはこの1編だけ、宿泊が必要なため会場はいつもの品川カポスではなく、埼玉県の別所沼会館です。
中浦和の隠れた名店
セミナーは午後スタートなので、集合時間より1時間以上早く着いてまずはお昼ご飯を食べられるところを探します。
すると、あるではないですか。JR中浦和駅を降りて別所沼会館へ向かうちょうど道沿いにラーメン屋を見つけました。
お昼なのに写真が夜なのはわけがあります。最後まで読むと分かります。
以前この合宿に参加した時はコンビニもなにも発見できずそのまま会場に到着してしまい、しかたなく施設内の高い昼食をとりました。今回はそんな苦い思いをせずに済みそうです。
やや重たい引き戸を開けて目の前の券売機で食券を買い、カウンター席に着きます。ほっと一息ついたところで何とはなしにお店の人の動きを眺めていました。
名店の接客術
店内はカウンターが8席に4人用テーブル席が2卓でわりとゆったりとスペースがあります。そこを店主ともう1人サポートのスタッフでまわしています。
できあがった麺をスタッフが運ぶたびに厨房から店主の声がひびきます。
「お待たせしました。後ろから失礼します。ごゆっくりお召し上がりください。」
声がけしながらも店主は作業の手を休めません。なんなら客席に背を向けて麺をゆでている時もあります。それなのに声がけが的確なタイミングでした。しかも聞き取りやすいしっかりとした発声です。
これはすごいものを見せられてしまったと思いました。
人間はまとっている皮膚という境界を越えて感覚を拡張することができます。
靴を履いていても靴底の感覚からそこが砂地なのか草地なのか分かりますし、車を運転していても車幅をぎりぎりで障害物をよけたりできます。テレビ番組などで達人が重機でワインをグラスに注ぐ芸当を見たことある人もいると思います。
この店主は店内のすべてに神経をはりめぐらせているのでしょう。さながら自分の体の一部のように。だから起きていることすべてが分かっていて的確な対応ができるわけです。むろん麺も大変に美味でした。
久しぶりにすごい芸当を見せてもらい大満足で店を後にして合宿会場に向かいます。去り際にも「お気をつけて、またよろしくお願いします」と声をかけていただきました。
鍼灸の触診とラーメン屋の接客術の共通点
さて合宿がスタートしました。
果たして講師の栗原が強調したのは触診の基本とそれに先立つ言葉がけの重要性でした。
触診は鍼灸師が体の状態をうかがうために身につけているべき基礎技術です。しかし触れられる側からしたらこれから何がおこなわれるか分からない状況でいきなり触わられるのは不安です。気になるところを本人にまず手で示してもらってからこちらが触れるなど、できるだけ自然で円滑な流れをもって触診に入れると「いま何をしているのだろう?」という不安や疑念を相手に抱かせずに済みます。そのような流れに誘導するために言葉がけが大事なのです。あのラーメン屋の店主はまさにそのお手本のような言葉がけをしていました。
次に触診ですがこれは皮膚という境界を越えて相手の体の情報を受け取ることです。私の理解ではこの「受け取る」というところが重要で、見にいくのではなく見えている、感じにいくのではなく感じられているのが理想です。例の店主はスタッフの動きやお客さんの状況をわざわざ見るのではなく、作業の合間にちらちら目の端に映っていた程度だと思います。入ってくる情報の邪魔をしない、これだけで見えてしまう、分かってしまう世界があります。
セミナーではこの後こまかく段階を踏んで触診の技術を学びましたが、いずれの段階においても感覚が開かれていて入ってくる情報を邪魔しないことは常にできている必要があります。
私も真剣に練習しました。
後日再訪
さあここまで読んだあなたは例のラーメン屋がどこなのか気になってしかたないことでしょう。
中浦和駅東口徒歩1分の「麺処 しかて」というお店です。
しかし残念ながら今月で閉店になってしまうそうです。なぜもっと早く来なかったのかと後悔しかありません。それで平日の仕事終わりにまた行ってきました。冒頭の写真が夜なのは二度目の来訪時に撮った写真だからです。
もう再びこの麺に会えることはないという思いで一口一口を大切にいただきました。新天地での店主の活躍を願いながら夜の中浦和を後にしたのでした。

鍼灸師。静岡県浜松市出身。趣味はオーケストラでのコントラバス演奏。
カポスでは副院長をしています。突発性難聴、声枯れ、喉のつまり等の耳鼻咽喉科関連症状、顎関節症が得意です。
音楽家の体の不調を解決したいとの思いから鍼灸師になりました。同じカポス内で「音楽のための身体調整しらべ」も担当しています。
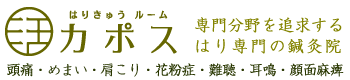

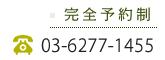




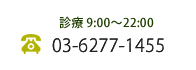
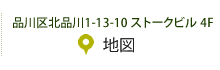

コメントを残す